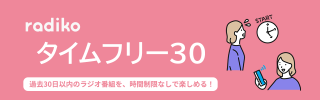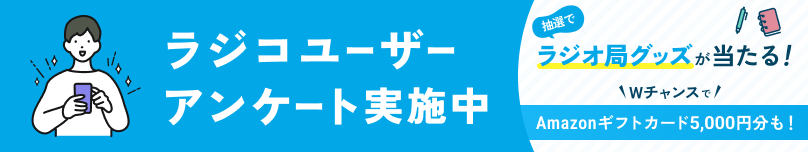トピックス
『わたしの図書室』10月30日、11月6日放送!文豪・室生犀星が、官能小説「蜜のあわれ」の表紙に熱望した突飛な図柄。そのメイキング・ストーリー。

ラジオ日本「わたしの図書室」では10月30日・11月6日の2週にわたり、室生犀星の短編小説「火の魚」を放送する。魚に対する犀星の偏愛が炸裂する物語。朗読は、日本テレビアナウンサーの井田由美。
【エロティシズム全開の小説「蜜のあわれ」】
「ふるさとは遠きにありて思うもの…」の詩で知られる室生犀星だが、実はかなり女性への執着が強かった。文豪にはありがちなことだ。1959年(昭和34年)に発表された小説「蜜のあわれ」は、妖艶な若い女性の姿で現れる金魚と、年老いた作家との秘密の生活を描いた官能的な物語。
今回、番組で紹介する短編小説「火の魚」は、その「蜜のあわれ」が単行本化される際、犀星自身が表紙の画として「金魚の魚拓」を熱望したところから物語が始まる。犀星のそんなムチャブリに応えたのは、誰だったのか? さて、その顛末は?
【室生犀星は魚好き!】
1889年(明治22年)、石川県金沢市で生まれた室生犀星は、私生児だったため寺にあずけられ、親の愛を知らずに育った。少年時代の辛い日々、家のそばを流れる犀川やそこに泳ぐ魚を眺めては慰めにしていた。犀星は「魚眠洞」という号でもわかるように、魚、それも生きて泳いでいる魚への偏愛を隠さない。
実際、犀星には、魚を題材にした作品が多い。詩では、「凍えたる魚」「七つの魚」「青き魚を釣る人」のほか、11月6日の放送で紹介する詩「魚」もある。小説では、「寂しき魚」「不思議な魚」「魚になった興義」など、いずれも魚が物語の中心で、ときに生き生きと、ときにもの悲しく描かれている。
【「火の魚」のモデル】
今回、紹介する「火の魚」は、「蜜のあわれ」が単行本化される際の、表紙の図柄をめぐる実話に基づくフィクション。主人公の作家「私」は、最近、「繚乱の衣装を身にまとった一匹の赤い魚の物語」を書き、いま、それが一冊の単行本になろうとしていた。彼は、表紙には「炎のような魚の絵」=「金魚の魚拓」がふさわしいと思いつく。このムチャブリを受けて立ったのは、ひとりの女性編集者「折見とち子」。物語は「私」と「とち子」の丁々発止のやりとりで展開していく。
【放送内容】
10月30日(木)・11月6日(木)23:30~00:00
朗読作品:室生犀星「火の魚」/詩「魚」
朗読:井田由美(日本テレビ・アナウンサー)
HPはこちら
番組終了後1週間は
のタイムフリーで